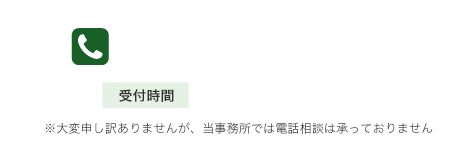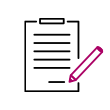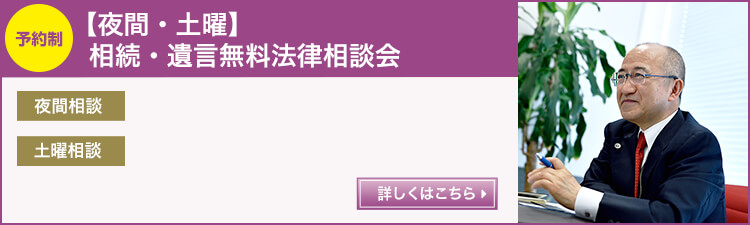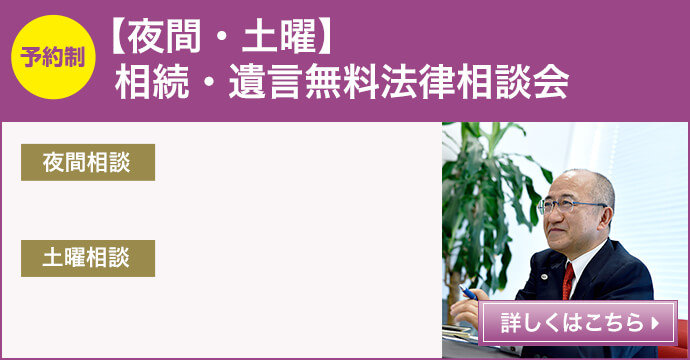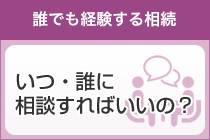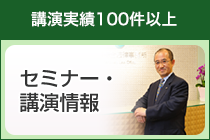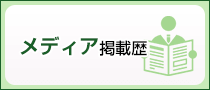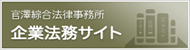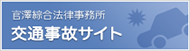失敗?成功!具体例から学ぶ「相続トラブル解決法」
 |
当事務所では、遺言や相続に関する講演会やセミナーの講師を務めることが多いためか、以前から遺言や遺産分割などの相続に関する相談や法的手続の依頼を数多く受けてきております。
そのような中には、もっと早く相談に来て戴ければトラブルにならなかったのにと思う失敗例もあれば、トラブルになりそうだったものを上手に切り抜けた成功例もあります。
相続問題は、人間は必ず死ぬがゆえに誰でも一生のうち数回は経験することになるものですが、できればトラブルとならずに円満に切り抜けたいもの。
|
例.1 遺言で最愛の妻に相続させる財産をすべて列挙したのに失敗?
子供はいないが仲の良い夫婦。夫は自分が死んだ後は自分の兄弟と妻が相続でもめないようにと2005年に遺言を作成。すべての財産を最愛の妻に相続させるつもりで、遺言には当時の不動産・預貯金をすべて列挙して妻に相続させると記載。兄弟には遺留分が無いため、これで夫死亡後も遺言で簡単に相続手続が行え安心のはずが…
実際の出来事
夫は2015年に死亡。妻は夫の遺言で自宅の相続登記や預貯金の相続手続を行おうとしたのですが、以前の郊外の戸建住宅を売却して駅前のマンションを購入、預貯金も外貨預金に切替えていたものがあり、それらは遺言に記載はないため遺言では相続手続が行えず、夫の兄弟と遺産分割協議を行わざるを得ないことに。しかも、夫の兄弟から法定相続分である合計1/4の権利を主張されることに!
すべての財産を妻に相続させるつもりであったのであれば、「すべての財産を妻に相続させる」の1行でOKだったのです。具体的に列挙する場合でも、すべての財産を漏れなく列挙は不可能ですので、最後に「他の財産もすべて妻に相続させる」と付け加えれば良かったのです。
遺言の書き方を説明した本も出版されており、遺言は自分一人でも作成できないことはありません。しかし、このように思わぬ落とし穴もありますので、弁護士に相談するのが安心です。相続で揉めてからの時間・労力・費用に比べれば、事前の相談がお得なのは明らかです!
例.2 遺留分を主張してくる次男に遺言への効果的記載で成功!
農家を継いでくれた長男に全財産を相続させたいと思っている父親。次男は自宅建築の際に相応の資金援助したのに遺留分を狙っている様子。遺言に長男の貢献の大きさを記載して次男は遺留分を主張しないように記載しようかと考えていますが…
実際の出来事
遺留分は、相続発生時の遺産に特別受益を加えた財産の1/2に法定相続分を乗じて算出しますので、貢献の大きさ・寄与分を遺言に記載しても遺留分対策とはなりません。次男が家に貢献していないと記載しても遺留分には影響しません。相続人から廃除できるような虐待を親に行ったのなら別ですが。
効果的なのは、次男に具体的にどのような資金援助を行ったかの記載です。資金援助は特別受益となり、その金額を前記で算出された遺留分額から差引いた金額が、次男が遺留分を侵害されているとして請求できる金額となります。
ですから、資金援助・特別受益の金額によっては、次男が請求できる遺留分は残っていないことになるのです。
親が亡くなってしまうと、資金援助等の特別受益を有しながら死人に口無しと認めない相続人もいます。しかし、遺言に具体的に資金援助等の特別受益となる事実を記載しておけば、認めないわけにはいかなかくなるのです。
当事務所で相談を受け、次男の特別受益を具体的に遺言に記載することにより、次男の遺留分侵害額請求を封じ込めることに成功しました!